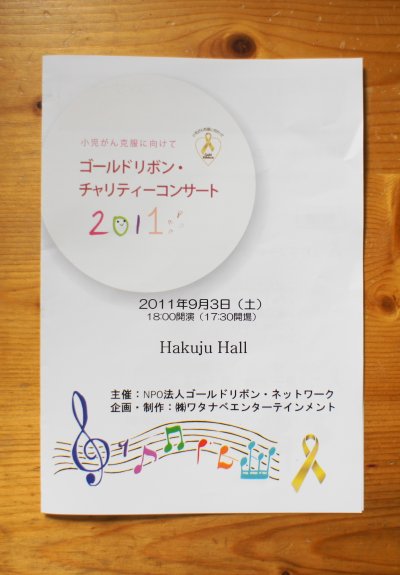地元の公立中学生の職場体験学習がありました。
当社は「製造業」なんですが、残念ながら工場は既に秋田に移転してしまっています。
そこで・・・担当のマーケティング部が考えた職場体験学習の題目がこちら
14×4が感じる「カワイイ」
街に出て様々な「カワイイ・かわいくない」を探してもらいました。 最終日、発表になった結果がこちら。
最終日、発表になった結果がこちら。
参加した14才4名からひとりずつ発表してもらいました。
 こちらの発表で印象に残ったのは「かわいくないもの=電線」
こちらの発表で印象に残ったのは「かわいくないもの=電線」
解決するためには、白くするのがよいとのことでした。
なくすことばかり考えていたので、なるほどと感心してしまいました。
 こちらは唯一の男子学生。
こちらは唯一の男子学生。
「カワイイ=ログハウス」この建物は自宅の近所なので、よく知っています。
弊社の雨といもついているうれしい建物です(笑)。
 「かわいくない=横断歩道の標識」 何だか堅すぎるとのこと。
「かわいくない=横断歩道の標識」 何だか堅すぎるとのこと。
女の子にしてランドセルを背負わせれば良いのではとのことでした。 確かに良いかも!
 最後はこちら
最後はこちら
左下に2つの建物があります。
「かわいくない=昔の和風建築」
「カワイイ=洋館&昔のポスト」
銅雨といが低迷している理由がよく判ります(涙)。
但しフォローの発言もありました。
かわいくないから不要なのではなく、伝統的なものも残すことも大切とのこと。
最後の1時間ほどの発表会だけ参加しましたが、
14才とは思えないほど、皆さんしっかりされていました。
職場体験学習というと、生徒が学ぶだけといったイメージもありますが、
やり方によっては、企業にとってもプラスになるようです。
参加された4名の中学生の皆さん、ありがとうございました。
 先日、あるフォーラムで親学を推進する高橋史朗先生のお話を伺う機会がありました。
先日、あるフォーラムで親学を推進する高橋史朗先生のお話を伺う機会がありました。