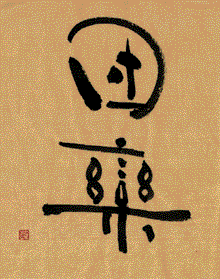ある 脳の学者 の話(家内より)
最近流行のDSなどのゲーム。
脳医学的にこのようなゲーム自体が
子供たちの脳に悪影響を与えることはないそうです。
但し、その先生は2年前からゲーム機を取り上げたとのこと。
理由は、ルールを自分たちで決めることが出来ないから。
みなさんは子供の頃、草野球などで、
・人数が足りないときの透明ランナー
・なかなか打てない子は下投げ
3ストライクを5ストライクに変える
など、ルールを変えて遊んだ記憶がありませんか?
ルールを調整しながらそれぞれの力が均衡する時
これが一番楽しいときであり、
この能力を子供の頃から鍛えておくことが大切だとのこと。
人と人がうまく関わり合っていく能力もこうした中で磨かれるんですね。